『トポス・ギア・タ・ぺディア』とは、ギリシャ語で『子どものための居場所』と言う意味です。Googl翻訳で探しました。
現在、子どもへの食事提供、遊び・学習支援、子どもシェルター、ヤングケアラー支援、子育て支援などの起業を計画中です。
子どもに関する様々な問題をワンストップで解決できる施設を構想しています。事業につても追い追い書きたいとは思いますが、今は準備中なので、大好きな読書の話でもしていきたいと思います。
A.Sニイル『自由な子ども』
(1953年)
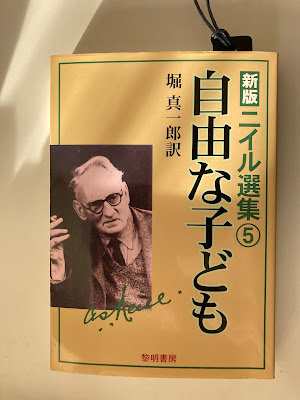 |
邦訳:1954年 霜田静志訳 講談社
1995年 堀真一郎訳 黎明書房 |
イギリスの教育実践家であるA.S.ニイル(1883-1973)は、サマーヒル・スクールの創始者として知られています。 私がニイルの著書を読んだのは、大学を卒業して地元の小学校で非常勤講師(アルバイト教員)をしていた時でした。こんなに自由な学校があるんだと大きな衝撃を受けるとともに、なんとか日本の公教育をサマーヒルに近づけたいと思ったものでした。
ニイルの著書は、どの本も学校教育のあり方を見直すために有用だと思います。本書は、抑圧された子どもと自律の子どもについての類い希な事例研究にもなっています。
いくつかニイルの発言を拾ってみましょう。
・不自由な子ども:彼は従順である。権威のいいなりになる。ほかの人の批判を恐れている。 こういう人、「子ども」だけではなく、「大人」にも多いですね。私はあまり従順とは言えませんが、権威にたてつくことは段々面倒になってきました。他者の批判を恐れています。不自由な「大人」ですね。
・反生命的な社会
性に関することはタブーという考え方は、古今東西あるようですね。ニイルは、それを反生命的と言い切ります。
・「条件づけされた子ども」と「自律の子ども」についての事例研究
日本人の大部分は条件づけされた子どもです。1950年代のイギリスでもそうだったことがわかります。理不尽なことは理不尽だと言える日本人になりたいですね。
例えば『緊急事態宣言』「自粛してください。補償はしません。」これって理不尽じゃぁないですか?
理不尽なことは、理不尽だと言えるようになりたいですね。
・サマーヒルは、遊びが最も重視される学校
・将来に対する心配が、子どもから遊ぶ権利を奪っている
・思春期の子どもたちが学校で勉強していることは、時間とエネルギーの無駄づかいだ。そのおかげで若者は、遊んで遊んで遊び抜くという権利を奪われている。
日本のお母さんたちが聞いたら腰を抜かしそうな言葉ですね。遊びは、実に様々な可能性を秘めています。遊びを通して培われる「ひらめき力」「想像力」「想像力」などがないと、技術革新の早い近代社会では、生き残っていけないかもしれません。ただテストに合格することが目的で、テストが終われば忘れてしまうような学習をニイルは「エネルギーの無駄づかい。」と言い切っているところが爽快です。
「生きて働く力」を身に付けてほしいと願っていました。
・学生たちは、…(中略)…しかし何かが欠けている。それは思考を感情に従わせる能力である。
ここでいう感情というのは、美意識や感性ではないかと思います。美意識って結局のところ「好き・嫌い」ですから。子どもは親のクローン人間でもないし、ましてや学校教師のクローン人間でもありません。
昔、尊敬する同僚から、「人は論理では動かんぜよぉ。」と言われたことがあります。「目からうろこ」の瞬間でした。
・子どもは、愛され自由であるなら、善良で正直な人間になるという真理である。
最も大切な子どもの権利こそは、愛され自由であることだと思います。
・これらのコロニーの職員に求められるいちばん大切な性格特性は、信頼を示す能力である。
・子どもは小さな大人ではない。だから自分たちだけの共同生活をするのが望ましい。
異年齢集団での遊びは、本当に大切だと思います。何故、日本の学校が同年齢の子供だけの集団を作っているのか、理解に苦しみます。
・私たちは、ほんとうに子どもを対等の人間として扱っているのに気がつく。つまり、子どもをまるで大人であるかのように扱かうのだ。
教員時代の私にとって、一番大切なことは子どもとの間に「ラポール(raport)仏」を築くことでした。「ラポール」というのは臨床心理学用語で、ぴったり当てはまるような日本語が見つからないのですが、敢えて訳語を見つけるならば「信頼関係+親密さ」といったところでしょうか?
ですから、私は可能な限り子どもと遊びました。中休みも昼休みも、たいてい20分です。若いときは良かったのですが、30歳を過ぎた頃から、20分間走り続けなければならない鬼ごっこは段々しんどくなりました。
後は、子どもとよくお喋りをしました。子どもにとって何より必要なのは「受容と共感」です。これは、子育てにも同じことが言えると思います。
サマーヒルでは、子どもも職員も皆ニックネームで呼びあいます。塾経営者だった時も、アルバイト教員だった時も、ニックネームで呼ばれていました。正規採用になって担任をするようになってからは『先生』と呼ばれていましたが、卒業生は、親しみを込めて『れいこちゃん』『れいちゃん』と呼んでくれるようになりました。
これから『トポス・ギア・タ・ペディア』の各部門のスタッフを見つけていきたいと思っていますが、何よりも子どもたちとの「ラポール」を大切に、自他の感性を大切にし、自分の頭で思考できる人を探していきたいと思っています。

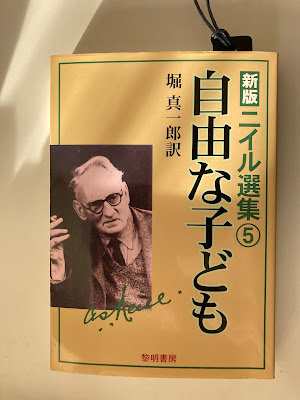



コメント
コメントを投稿